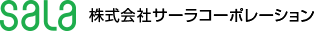代表取締役社長 兼 グループ代表・CEO
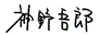
サーラグループは1909年の豊橋瓦斯、翌1910年の浜松瓦斯設立からはじまりました。当時、街角を照らすガス燈は豊かな暮らしの象徴だったと聞いています。その後、地域とともに戦後の復興から高度成長へと歩みを進めていく中で、ガス供給によって社会インフラに貢献するだけでなく、エネルギー全般やエンジニアリング、住宅、輸入車販売、金融、不動産に至るまで、まさに「暮らしに関わることはなんでもやっていこう」という姿勢で、ガス供給から総合生活産業へと徐々に事業を拡大してきました。
私は大学卒業後に金融機関で海外赴任などを経験した後、1990年に地元の豊橋に戻り、中部ガス(現サーラエナジー)に入って現場の仕事に勤しみました。2000年にLPガスや石油を扱うガステックサービス(現サーラエナジー)の社長に就任し、グループの再編や古くからあった事業の再構築などに尽力しました。そこでは「21世紀を展望し、基本理念に掲げる豊かな社会の実現に向けたプロセスをどう作っていくか」を念頭に、ただ闇雲に事業を広げるのではなく、既存事業のブラッシュアップと新しい取り組みのトライ&エラーを繰り返しながら、一歩ずつ地道に成長してきたという感覚です。
持株会社制度が解禁されて間もない2002年に純粋持株会社であるサーラコーポレーションを設立しました。そしてグループ経営の質向上を求め「生活にファインクオリティ。SALA」というブランドメッセージと、「サーラ品質経営」「グループ価値経営」「人間力経営」「共創経営」「エリア貢献経営」「株主価値経営」という6つのグループバリューを制定しました。さらに2016年には、上場関連会社であった中部ガス、サーラ住宅を完全子会社化し、各社の多様なサービスを最適な形で提供できる、現在のサーラグループの体制を整えました。
こうした変遷の根本には、地方のガス会社はエネルギーの供給に専念するだけでは十分でなく「常に地域・社会の発展を考えなければ未来がない」という危機感がありました。人口減少社会が懸念され始めた2000年の当初からずっと考えてきたことですが、実際に人口減少が進行し始めた今、その思いはさらに強まっています。豊かな暮らしと社会の発展のためにどのような事業を立ち上げるべきなのか。その判断は社会を見つめる“洞察力”から生まれると思います。時代の変遷の中で企業としての存在価値を追求していけば、おのずとやるべきことは見えてくるものです。
当社のコアエリアである愛知県東部・静岡県西部地域は、東京と大阪のちょうど真ん中にある“日本のへそ”です。農業などの第一次産業はもちろん、製造業などの第二次産業も非常に盛んです。両地域の製品出荷額は11兆円を超える規模があり、そのポテンシャルを活かすためのプラットフォームが必要だと考えてきました。
一方で、2003年には豊橋駅前の大型商業施設が撤退し、まちなかから賑わいが失われていくにつれ、地域に必要な力が足りていないと感じることもありました。そこで自治体や地元経済界からもお力添えをいただき、背中を押してもらう形で豊橋駅前の再開発に携わり、2008年にホテルアークリッシュ豊橋を含む複合施設「ココラフロント」を開業しました。その発想の中心にあったのが、豊かな東三河のイメージです。東三河には豊かな山があり、海があり、まちがあります。交通の要衝として、東三河全域からはもちろん、東京や名古屋、世界各国からも人々が集います。私たちはこの駅前再開発プロジェクトを「東三河元気化プロジェクト」と名づけ、東三河の玄関にあたる場所として、「ここからはじまる」「心から楽しむ」を開発コンセプトに定めました。
地方創生には地元の人材や視点だけでは不十分です。「社会を変えるのは、若者、バカ者、よそ者」といわれることもあります。まさにその観点で、ローカルの歴史や文化、豊かな自然や食材を活かしながら、グローバルに活躍する外部のクリエイターやデザイナーの協力を得て、皆が集い、暮らし楽しむ“東三河のリビングルーム”を作り上げようとプロジェクトが始動しました。
その後、2009年の「ココラアベニュー」、2021年の「emCAMPUS EAST(エムキャンパス東棟)」に続き、今年の4月には「emCAMPUS WEST(西棟)」など、新たな複合施設が完成しました。ただ新しいハードを作り、営利目的でテナントを管理するだけでは、まちづくりはうまくいきません。外部の力も借りながら、地域の歴史や文化、豊かな自然や食材を改めて評価し、未来に息づくような価値を生み出す。それこそが持続可能な地方創生だと思います。
最近ではこうした動きの中で「東三河フードバレー構想」が生まれ、emCAMPUSやホテルアークリッシュ豊橋などを中心に、地元の生産者や料理人など「食」や「農」に関わる多彩な人材が交流を深めています。emCAMPUSの屋上には有機栽培農園も作られ、こだわりの農産物を育てる活動も始まりました。こうした取り組みは、今はまだ事業というには及びませんが、これからの展開を非常に楽しみにしています。
このような取り組みの本質は、地域ならではの価値を創り上げ、「ここに住みたい、働きたい」と感じていただけるまちづくりにあります。これは東三河エリアに限ったことではなく、当社が展開するすべてのエリアに貫かれている本質的なテーマです。まちの活性化と当社の事業は表裏一体と言っても過言ではありません。
今日ではどのような事業においても、気候変動問題や生物多様性への目配りが必要不可欠であり、カーボンニュートラルな社会を創造するための積極的な取り組みは、もはやグローバルスタンダードになっています。当社でも、地域における環境に配慮した先進的な取り組みを続けてきました。
たとえば2016年に電力小売事業に参入した後、2019年にはバイオマス発電所の稼働を開始しました。当初、地域の間伐材(燃料)は、それほど多くは調達できないと考え、主原料はPKSと呼ばれるパーム椰子殻を調達していますが、今では間伐材も当初予想の約10倍に当たる12,000tほどが確保できるようになり、地産地消のエネルギーを生み出す試みが、少しずつ軌道に乗ってきました。
一方、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーは、気象条件などによって発電量にばらつきがあり、せっかく発電した電気が使われない出力制御が頻発しているのが大きな課題です。そこで当社は系統用蓄電池に投資し、大規模な蓄電施設によって供給を平準化し、再生可能エネルギーを最大限活用できるように貢献していきます。
また、電力事業以外の取り組みでは、国内のカーディーラーで初となる実質的にCO₂を排出しないカーボンニュートラル店舗の実現や、建築から解体までのCO₂収支をマイナスにする戸建住宅の開発・販売、ビルのZEB化に力を入れています。このように当社は地域に根ざしたアプローチでカーボンニュートラル社会に貢献していきたいと考えています。
2023年度を振り返りますと、コロナウイルスの感染法上の分類が5類に移行し、経済活動の回復が進んだ一方で、多発する自然災害やウクライナ情勢不安、円安等の影響で先が見通せない混沌とした状態が続きました。このような状況のなか、2023年度のサーラグループの業績は、エネルギー原料価格の高騰を反映して過去最高の売上高を記録しました。一方、利益面はガス販売量の減少や住宅販売が苦戦した影響により、営業利益は残念ながら減少しました。
ただ、こうした不透明な状況の中でも、これからの持続的成長に向けて改革を進められた一年だったともいえるでしょう。静岡県内では初となる系統用蓄電池の建設や、国の環境基準を先取りした戸建て注文住宅の新商品開発、浜松市内のアウディ、フォルクスワーゲンすべての店舗の脱炭素化達成など、カーボンニュートラル関連のプロジェクトが前進しました。サステナブルな成長を目指した新たな試みは、今年度以降も各事業を牽引していくと考えます。
2030年ビジョンの達成に向けて、現在は第5次中期経営計画の2年目を迎えています。ここでは、持続的な成長に向けて積極的な成長投資をしていくことが大きなテーマです。先ほど述べた系統用蓄電池などの電力ビジネスへの投資のほかに、サーラグループのお客さまIDを統合し、業務プロセスの効率化とお客さまサービス向上をねらいとするDX投資に力を入れています。これまではグループ各社がそれぞれお客さま情報を保有してサービスを提供していましたが、これらのデータを1つに紐づけて統合することにより、地域のお客さまとサーラを結びつけるプラットフォーム(基盤)が完成します。新システムは2025年から稼働を開始する予定で、このプラットフォーム上に、外部の企業、大学、行政機関との共創により様々なサービスを追加していくことでより豊かな暮らしを提供していくことができると考えます。そのほか、暮らし・住まい分野やグループの成長を支える人材への投資も積極的に取り組んでいきます。
当社は2002年に持株会社として設立以来、グループの資本再編とグループ一体経営のシナジーを通じて一歩ずつ着実に売上高・営業利益を伸ばしてきました。今後、2030年には売上高2,800億円、営業利益120億円の達成を目指しています。一方、資本効率の観点では、利益が積み上がり自己資本が増加したことに伴い、ROE(自己資本利益率)は8%程度で伸び悩んでいる状況にあります。そこで、当社は2030年ビジョン実現に向けて、改めて2024年から2030年までに得られるキャッシュ・フローをどのように配分するのかというキャピタル・アロケーションについて取締役会や常勤役員で構成される経営会議において議論を重ねました。その中で、最も重要なのはさらなる成長への投資を加速していくことであると考えています。電力ビジネスの拡大や、暮らし領域の拡充のためのM&A、ベンチャー企業とのアライアンスなどの成長投資にキャッシュ・フローの2分の1を投じます。成長投資に加えて維持更新投資や株主還元の強化により資本収益性の向上を図り、2030年時点にはROE10%以上を目指します。また、自己資本比率については40%から50%程度にコントロールます。
私たちは2030年ビジョンの目指す姿として「SALAブランドの確立」「質の向上」「住まい分野の飛躍的成長」「自ら考え、行動する人づくり」「社会価値向上」の5つを掲げています。社員一人ひとりが持てる能力を最大限発揮できる制度や環境を整え、社会課題やお客さまの課題解決に次々にチャレンジします。また、システムや業務プロセスの質を高めて生産性を高め、エネルギー以外の暮らし・住まいの領域を重点的に拡大します。その結果、「私のまちにSALA、暮らしとともにSALA」のキャッチフレーズにあるように、地域に浸透して、暮らしや社会を豊かにする会社となることを目指しています。